|
|
| 新聞記事より、出版・印刷業界の動きに関するものをピックアップしました。 |
 今年も残すところ三週間あまり。企業が来年のカレンダーを顧客や得意先に配布するシーズンだが、目下の不況で部数を減らしたり、壁掛けから卓上に切り替える企業が増えている。イメージ重視で現状維持の小売店があるものの、経費削減は「暮れのごあいさつ」にも及んでいる様子だ。 今年も残すところ三週間あまり。企業が来年のカレンダーを顧客や得意先に配布するシーズンだが、目下の不況で部数を減らしたり、壁掛けから卓上に切り替える企業が増えている。イメージ重視で現状維持の小売店があるものの、経費削減は「暮れのごあいさつ」にも及んでいる様子だ。
トヨタ自動車グループの豊田通商は来年用の国内向けカレンダーを、昨年暮れに配布した「2009年版」よりも2000部ほど少ない2万8千部に減らした。「この不況。作るかどうか迷った」(広報)が、企業のPR効果などを期待して、廃止にはしなかった。
異変はトヨタ自動車でも起きた。フォーミュラワン(F1)世界選手権からの今季限りの撤退に伴い、F1の写真などをデザインしたモータースポーツカレンダーの制作を取りやめた。
一方で、「高級感」「顧客サービス」に敏感な小売店には現状維持が目立つ。名古屋市の主要百貨店では、ジェイアール名古屋高島屋や三越などが「毎年楽しみにしていただいている」と、昨年通りの対応だ。
「エコ」が一段と重視されそうな10年。10月には名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開かれることもあり、中部電力は里山のイラストなどをあしらって環境重視を打ち出した。東邦ガスは名古屋港などの風景画をデザインし、地域密着をPRしている。
名古屋市内のカレンダー販売会社は今年の傾向を「不況になると真っ先に制作費用が削られる。昨年よりも厳しい」と実感する。大手印刷会社は「部数を2〜3割減らしたり、大型サイズから小型の卓上サイズに切り替えるケースもある」と、企業の経費削減努力を代弁する。
ただ、企業カレンダーの減少傾向は不況の影響だけではなさそうだ。愛知県刈谷市の自動車整備会社は、昨年から配布部数を50部減らし、250部にした。「携帯電話でスケジュール管理をする人が増え『カレンダーが欲しい』という顧客が減った」(経営者)と、時代の移ろいも映し出している。 |
2.凸版の今期 コスト削減額積み増し 100億円、年392億円に |
凸版印刷は2010年3月期のコスト削減額を約100億円積み増し、年392億円とする。期初計画は290億円だったが、上期(09年4〜9月期)の削減額が想定を上回る186億円に到達。下期は原価率改善などをさらに進め、200億円超のコスト削減を目指す。
原価率改善によるコスト削減は284億円の計画。うち、エレクトロニクス事業で105億円を見込む。ガラスの再生などで材料費を減らすほか、設備投資を抑制し減価償却費を圧縮する。半導体フォトマスクの製造拠点を集約した効果も見込む。
印刷事業と包装材などの生活環境事業では157億円を見込む。外注費の抑制や材料費、物流費の削減を進める。
人件費は100億円超を削減する。人材配置の見直しを推進。残業時間も削減する。上期だけで51億円を削減したが、下期は57億円を見込む。
本業の印刷事業が苦戦し、10年3月期の連結売上高は1兆5670億円と前年同期比で3%減となる見通し。生産体制の見直しも進め、経常利益は40%増の350億円、最終損益は70億円の黒字(前期は77億円の赤字)を見込む。 |
3.竹田印刷 電子看板に参入 家電と協業 企画制作請け負い |
印刷と広告企画を手掛ける竹田印刷は電子看板(デジタルサイネージ)事業に参入する。電子看板に載せるコンテンツ(情報の内容)の企画制作を、電子看板メーカーから請け負う。デジタルサイネージ市場は2012年に830億円と、08年比4割近く増えるとの試算がある。竹田印刷はまず2年後に数千万円の売り上げを目指す。
同社はこのほど、関西の大手家電メーカーと共同で、デジタルサイネージを小売店舗に設置して販売効果を測定する実験を始めた。液晶画面に表示するデジタル画像の時間や内容によって、販売増に結びつくかを調べ、今後の営業に生かす。
看板本体や配信システムの開発製造は家電メーカーが、竹田印刷は画像のデザインや制作を担当する。顧客は百貨店やホテルなどを想定。両社で連携しつつ顧客店舗内に導入を呼びかける。
調査会社の富士キメラ総研によると、08年のデジタルサイネージ市場は600億円。景気悪化で09年は横ばいを予測するが、広告内容を柔軟に替えられる機能性を武器に10年以降は成長が続くと同総研はみている。
竹田印刷は、新聞やカタログの印刷事業のほか、長年培った広告チラシデザインの技能を生かして、広告の企画制作事業も手掛ける。デジタルサイネージは広告事業と関連性が高いとみて、新事業を立ち上げる。 |
| 富士ゼロックスは15日、オフセット印刷並みの高画質で出力が可能なデジタル印刷機事業の連結売上高を2014年3月期に09年3月期比2.2倍の3000億円に拡大する目標を発表した。より画質を高めた新型機を10年1月に投入。必要な時に必要な部数を印刷できるデジタル印刷機の利点を訴え、印刷会社や複合機の顧客企業などへの売込みを急ぐ。 |
5.100%生分解包装フィルム 廃棄後、肥料に フタムラ化学 |
| フィルム大手のフタムラ化学は、完全に肥料化できる生分解フィルムを開発した。植物性のセロハンフィルムに加えてインクやラベル、接着剤も土中の微生物によって分解され、堆肥として還元できる。主に食品包装向けフィルムとしての活用を見込む。まず廃棄物処理の先進国である欧州で拡販し、販売動向を見極めながら国内への販売にも踏み切る計画だ。
生分解フィルム「グリーンフューチャー」を開発した。ラベルのインク技術の開発に東洋インキ製造、印刷技術に凸版印刷が協力した。セロハン分野で競合するフィルムメーカーの製品では難しかったカラー印刷や高い耐久性も実現した。カラー印刷が可能な包装材を完全に肥料化できる。
トウモロコシなど植物由来の原料であるポリ乳酸を使ってフィルムを製造。食品包装に使うカラーラベルやラベルの接着剤なども肥料化が可能で、生ごみとして捨てることができる。土中の微生物の働きで1カ月程度で分解されるという。
まずは商社経由で欧州の食品包装材メーカーに販売する。欧州では、一般家庭の庭先にコンポストと呼ばれる肥料化装置を設置していることが多く、食品ごみと一緒に廃棄して肥料として活用してもらう。エコ意識の高い消費者向けに需要が見込めるという。欧州と豪州、米国でも販売して今後1年間で20億円の売上高を目指す。
食品包装のほか、生分解可能な樹脂プラスチック向けラベルシールなど環境対応型商品を生産するメーカーなどにも売り込む。パソコンなどIT(情報技術)機器にも生分解製品は徐々に浸透しつつあり、環境適応を前面に打ち出しフィルムシート分野でシェア拡大を目指す。 |
6.DICの米子会社 営業利益75億円 今期、連結業績改善に寄与 |
DICの米印刷インキ子会社、サン・ケミカルの2010年3月期営業利益は前期比66%減の75億円となる見通しだ。09年4〜9月期(上期)は3億円の営業赤字だが、下期は工場再編などのリストラ効果が寄与する。サン・ケミカルはDICの連結売上高の4割を占める主要子会社で連結業績の改善にもつながる。
クリスマス商戦などで10〜12月に印刷インキの需要が回復傾向にあることも寄与する。棚卸し資産の評価方法が先入れ先出し法だったため上期は原材料高の影響を受けたが、下期は在庫コストが小さくなった。
DICの下期連結営業利益は前年同期比51%増の123億円の見通し。サン・ケミカルの業績回復に加え、中国の家電向け合成樹脂など高付加価値品が好調を維持する。ただ、樹脂を扱う欧州子会社のリストラ費用がかさむため、最終損益は30億円の赤字(前年同期は75億円の赤字)となりそうだ。 |
7.アスクル純利益15億円 コスト削減で予想上回る 6〜11月 |
アスクルが16日発表した2009年6〜11月期連結決算は、純利益が前年同期比20%減の15億円だった。景気低迷でオフィス向け通販事業が伸びず、売上高は従来予想と比べ減少幅が拡大。個人向けネット通販事業を刷新したことで減損損失を計上したものの、商品調達コストの削減や新事業開始に伴う費用負担を抑制した結果、従来予想を3億円超上回った。
売上高は3%減の935億円と予想を49億円下回った。オフィス向け通販の利用客は引き続き増えているが、価格の高いオフィス家具の販売が23%減り、販売単価が低下した。
経常利益は4%減の35億円と従来計画を10億円上回った。新サービス導入にかかるシステム開発費用などを計画よりも圧縮したことや、諸経費の削減で販売管理費を抑えた。
10年5月通期は売上高を前期比7%増の2030億円、純利益を同27%減の33億円に据え置いた。大企業向けの購買代行サービスや中国・上海でのオフィス向け通販などの新事業が拡大。売上高は増えるものの、先行投資負担が重荷となる見込み。 |
経済産業省は24日、大日本印刷が産業活力再生特別措置法に基づき提出した、生産性と省エネルギー向上を目指す「資源生産性革新計画」を認定したと発表した。
計画では、堺市に新設する液晶用カラーフィルター工場に、生産性が高く、環境西濃に優れた生産設備を導入する。今回の認定で、生産設備の導入費用で計画に該当する部分を初年度に全額償却できる措置が受けられる。 |
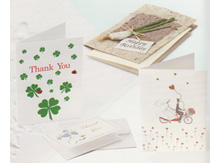 誰かにメッセージを伝えようとした時に、同じ想いを抱く仲間がほかにもいたら・・・。「色紙」に寄せ書きをする方法がある。グループによる意思伝達ができるこの紙も、コミュニケーションツールとしては興味深い存在だ。(略) 誰かにメッセージを伝えようとした時に、同じ想いを抱く仲間がほかにもいたら・・・。「色紙」に寄せ書きをする方法がある。グループによる意思伝達ができるこの紙も、コミュニケーションツールとしては興味深い存在だ。(略)
平判は概ね、オモテ面が奉書紙、ウラ面が砂子入りの紙(金銀の斑点模様が付いた紙)、芯がボール紙となっており、製造に際しては、まず奉書紙に色柄を印刷。次いで3枚の紙を貼り合わせ、1か月ほどの時をかけて乾燥させた後に断裁し、金色などのテープ(蒸着紙)を縁に巻いて仕上げられる。(略)
ただし、色紙のうち両開きタイプだけは、古紙パルプを主原料とした、一般的なチップボールが使われる。折り返しの面積が、左右半分ずつになってしまう両開きで、紙の浮き上がりを防ぐには、ある程度の重みが必要になるからだ。一見シンプルな構造に見えながら、在るべき形状の保持や使い勝手向上のため、種々の工夫が施されているのが、色紙という商品であるようだ。(略)
日本の生活文化に根付いた色紙は、色も形も、伝える想いも、さらに“色々な紙”へ。今ふたたびの進化を遂げようとしている。 |
丸善は8日、2010年1月期の連結最終損益が3億円の赤字(前期は4億4200万円の赤字)になりそうだと発表した。従来予想は5000万円の黒字だったが、一転して赤字となる。主力の書籍販売が苦戦しているうえ、大学向けの図書館運営なども想定を下回った。
売上高は前期比6%減の915億円の見通しで、従来予想を70億円下回る。
消費者の節約志向が高まり、書籍の購入頻度が低下したことを背景に、強みを持つビジネス書を中心に売り上げが落ち込んでいる。企業向けの書籍販売も、顧客の経費削減で振るわない。アマゾン・ドット・コムなどネット販売の台頭も響く。
来客数が多い夕方にパート・アルバイトを集中させる一方、客足が少ない時間帯の販売員を抑えて人件費を削減するなど、販売管理費の圧縮を進めている。しかし減収には追い付かず、経常損益は2億5000万円の赤字(同4億7800万円の黒字)になりそうだ。
同日発表した09年2〜10月期連結決算は、売上高が8%減の639億円、最終損益が15億円の赤字(前年同期は10億円の赤字)だった。 |
2.はるやま 女性誌とスーツ企画 20歳前後向け 誌面で商品紹介 |
はるやま商事は9日、講談社の女性ファッション誌と共同企画した若年女性向けスーツを発売すると発表した。丸みを帯びたデザインにしたほか、雑誌の誌面で商品紹介するなどで認知度を高める。男性向けスーツ市場の縮小を受け、はるやま商事は女性向け事業を強化している。新ブランドの投入で2年後に女性商品の売上高を50億円と倍増させる。
講談社の「ViVi」と組み、新ブランド「ViVifleurs(ヴィヴィフルール)」を立ち上げる。同誌の購買層と同じ10代後半〜20代前半に売り込む。
スーツやコートなど15種類で、価格はジャケットで2万円程度と従来商品より約1割低めに設定した。全国の「紳士服はるやま」など直営店で販売する。 |
3.講談社・くまざわ書店 店頭ポスターでポイント付与 携帯で読み取り |
| 講談社と書店チェーンのくまざわ書店グループ(東京都八王子市)などは携帯電話を使った販売促進策を始める。書店内にICカードリーダー付きのポスターを設置。来店者が非接触IC技術「フェリカ」を搭載した携帯をかざせば現金などと交換可能なポイントを付与する。来店客数の減少に歯止めをかけ、書籍販売の増加につなげる。 |
4.教科書 再び開く 大人向け 歴史や数学 年末年始、お金かけず勉強 |
| 歴史や数学などももう一度勉強したいと考える大人向けの教科書や学習雑誌が人気だ。夏ごろから相次いで登場した高校の教科書を再編集した本などに加え、学研ホールディングスの「科学」は小学生向けが来春休刊なのに大人向けは入手が難しい号もある。学ぶ意欲はあっても時間や手ごろな題材がなかった人たちに受け入れられている。
「学生時代に勉強したはずなのにすっかり忘れている。年末年始にでも読んでみようかなと思って」。20代後半の男性は都内の書店で「もういちど読む山川世界史」(1575円)を手にした。訪日外国人向けの旅行会社に勤めており、「お客さんの国や宗教の歴史を知って仕事に生かせれば」と話す。
同書は高校生向けの歴史教科書で知られる山川出版社が既存の教科書を再構成し、8月末に刊行した。丸善丸の内本店(東京・千代田)では人文書の売れ筋コーナーに並び、日に5〜7冊程度売れており、日本史版の「もういちど読む山川日本史」も同様だ。
懐かしんで手に取る人や「信頼感があるので世界の情勢を読み解く副読本として買い求める人も多い」(同店)ようだ。山川出版社によると両方とも発行部数は4万部に達し「予想を上回る売れ行き」という。
こうした動きはブームの歴史に限らない。学研の「大人の科学マガジン」は子供向けの「科学」同様、ミニエレキギター、簡素なコンピューターといった自ら組み立てる付録が付く。10月末発売の35ミリ二眼レフカメラは5.7万部発行し、さらに3万部の増刷をかけたほどの人気だ。
欲しい号の在庫確認に同店を訪れた40代の男性は「子どものころ『科学』を定期購読していたので懐かしくて時々買う」と話す。学研によると購入者の多くがこの男性のようにかつて子供向けで学んだ経験を持つ40代。きっかけとなった小学生向けが少子化で2010年3月発行号で休刊するのとは対照的だ。
日本実業出版社が7月に発売した「もう一度高校数学」(高橋一雄著)。「統計などを仕事で使う人が増え、基礎となる高校数学を学び直したいという要望が多くなった」ため、高校3年間で学ぶ要素を1冊にまとめ出版を決めたという。2940円で安いとはいえないが、約3万5千部を発行し「ヒット商品に育ちつつある」(同社)。
こうした教科書・学習雑誌の人気は大人の学習意欲の高まりと手軽な題材が合致したことが背景にある。内閣府の20歳以上の3000人を対象にした2008年7月発表の調査では「生涯学習をしてみたい」人は70.5%で3年前を6.5ポイント以上上回った。だが実際に「したことがある」は47.2%で微減。「仕事や家事で忙しくて時間がない」人が64.3%を占めた。
だが景気の悪化で時間に余裕のある人は増えた。日本生産性本部の柳田尚也主任研究員はこのところ「レジャーに使うお金を引き締め、日常の延長上の余暇に時間をかける傾向にある。教科書を使い、自分で体系的に学ぶのはその流れに合致している」と指摘する。
調査会社、アイシェアの今年10月の20〜40代を対象にしたネット調査では、大人になってから「興味のあることを新たに勉強してみたいと思ったことがある」人は86.7%。学習に対する意欲は高い。一連の教科書などはこうした意欲の受け皿となっているようだ。 |
1.電子書籍混戦 米、出版・新聞5社提携 対「キンドル」アップルも参入? |
米国で電子書籍端末を巡る競争が激しくなってきた。首位のアマゾン・ドット・コムの「キンドル」を追いかけ、異業種やベンチャー、出版大手が相次ぎ参入。アップルの新端末の投入も現実味を帯びてきた。ただ、本や新聞が手軽に読める電子書籍の市場は離陸したばかり。しばらくは混戦模様が続きそうだ。
カリフォルニア州のシリコンバレー。3日、今年の有力製品を振り返るイベントに技術者ら数百人が集まった。新製品情報に強いコラムニストは「アップルの次の製品は今までにないモノになる」と予言した。
ネット上などで浮かぶ新製品の姿は持ち運び可能な小型端末。高機能携帯電話「iPhone(アイフォーン)」より大きく、タッチパネル方式で簡単に操作できるとみられている。アップルは携帯音楽プレーヤー「iPod」、アイフォーンとヒットを飛ばしてきたが、「次に狙う市場は電子書籍」と言われる。
同社は「年内に新製品を投入する予定はない」(マーケティング担当者)と強調するが、電子書籍にも対応する携帯型の端末が来年登場するとの見方は業界内で根強い。
電子書籍はネット上から書籍や新聞のデータを取り込み、どこでも専用端末で楽しめる。普及台数は累計で300万台前後。アマゾンが6割以上のシェアを握り、ソニーなどが追撃する構図だ。米調査会社イーンスタットは2013年の世界出荷台数が2860万台に伸びると予想する。
急成長を見込んだ新規参入は広がる。書店大手バーンズ・アンド・ノーブルは「Nook(ヌック)」を年末商戦に合わせて発売した。新興のプラスチック・ロジック(カリフォルニア州)も英紙フィナンシャル・タイムズなどからコンテンツ協力を獲得。年明けに詳細を発表する予定だ。
新聞や出版など伝統的メディアはネット上で無料で読める記事が増え、業績は苦しい。電子書籍は新たな収益源の一つだが、アマゾンとの距離感は微妙だ。配信収入の7割をアマゾンが得るという契約に不満がくすぶり、ニューズ・コーポレーションのマードック会長は「良い取引ではない」と批判する。
メディア大手は独自の事業モデルを懸命に探る。新聞・雑誌大手ハーストが系列ベンチャー「スキッフ」で広告の掲載機能も備える端末と配信サービスを開発。購読料と広告料の双方を収入にできる利点をメディア各社に訴え、来年参入する。ハースト、タイムワーナー(TW)傘下のタイムなど雑誌・新聞大手5社は8日、ネット配信などの協力を発表した。
端末の魅力、コンテンツの幅、配信サービスの使い勝手――。デジタル時代のコンテンツ事業は総合力が決め手となる。伝統的なメディアも含めて電子書籍の勝者はまだ確定していない。 |
 |
| インターネット時代への対応を迫られる出版界で、電子配信の試みが相次いで始まっている。ネット検索最大手の米グーグルによる書籍検索サービスなどの外圧も加わり、活字文化が大きく変わりつつある。
「2年前なら無理だった」。来年6月から「小田実全集」全89巻が電子書籍として刊行される。版元は講談社。担当するデジタルメディア推進部の吉沢新一部長は「今だから実現した企画」と説明する。そもそも「“紙”の個人全集は商売として成り立ちにくい」。この時機に電子出版に乗り出す背景には、高速ネットの普及、使い勝手の良い電子書籍端末の登場など技術環境の変化がある。
例えば米ネット販売大手アマゾン・ドット・コムが今秋に日本で発売した電子書籍端末「キンドル」。目が疲れにくい電子ペーパーなど「紙の本を読むのに近い感覚で扱える」と出版関係者も総じて及第点を与える。まだ日本語には対応していないが、デジタル時代の本格的到来を告げた感がある。
今月2日夜、東京・神田にある東京電機大学の一室に200人を超す出版関係者が集まった。中小出版社の組織、版元ドットコム主催の電子書籍勉強会だ。電子書籍で実績のある扶桑社の担当者らが講演。活発な質疑で、会は予定の2時間を30分近く超えて続いた。
勉強会で司会役を務めたポット出版の沢辺均社長は「電子書籍は明らかに便利。シェアが増えていくことは間違いない」との見方を示す。「既にデバイス(機器)は十分に実用レベルに達しているので、後はコンテンツ(中身)だけ。数年後にはほぼすべての本が電子配信されるようになるのではないか」。
電子出版の動向を伝えるネット上の雑誌「マガジン航」の編集長で評論家の仲俣暁生氏は「紙かネットかという議論より、はるかに速く現実が先に進んでいる」と指摘。対応に追われる業界の様子を「黒船が来たような状況」と例える。
出版科学研究所によると国内の書籍・雑誌の推定総販売額は1996年の2兆6563億円をピークに減少に転じ、昨年には2兆177億円まで落ち込んでいる。“紙”が売れない状況で、ネットに活路を探らざるを得ない事情がある。
日本雑誌協会は来年1月、雑誌記事を電子配信する実証実験を始める。大手を中心に100誌が参加し、著作権処理の仕組みやビジネスモデルのあり方を検討する。実際に事業を始めれば紙媒体への影響も懸念されるが、同協会の高橋憲治事務局次長は「危機感は非常に強い」と話す。
まさに黒船のように出版界を揺さぶった米グーグルの書籍検索サービス問題も続いている。あらゆる本をデジタル化し、検索・閲覧可能にすることを目指す事業は曲折の末、ひとまず日本の書籍を対象外とする形になったが、残したインパクトは大きい。
日本文芸協会の坂上弘理事長は「グーグル問題は終わったと拍子抜けする方もいるが、そうではなく、これからの出版業界に強い影響力を持つモデル」と今月に理事会で訴えた。実際、同協会は日本書籍出版協会や国立国会図書館などとともに、グーグルに準じた構想を合法的に実現する制度の検討を始めた。「デジタル化はもろ刃の剣」(書協の小峰紀雄理事長)と警戒感も残るが、流れは止まりそうにない。 |
| 放送局向けシステム開発の北海道日興通信(札幌市、高間猛社長)は画像処理システムの米トパーズ・ラブズ(本社テキサス州)と提携し、同社の画像補整技術を使ったソフトの国内販売を始めた。パソコンに取り込んだ画像から特定の人や物の画像だけを切り抜き、放送素材や印刷物として利用できる。テレビ番組制作会社や印刷会社などに売り込む。 |
4.ソニー 米で新聞・雑誌配信 電子書籍端末に ニューズと協力 |
ソニーは17日、年内から米国で電子書籍端末「リーダー」向けに新聞・雑誌コンテンツの配信をはじめると発表した。「ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)」などを抱える米ニューズ・コーポレーションと協力、同社グループからの独占コンテンツも売り物にする。従来は書籍のみ配信していたが、コンテンツの幅を広げる。電子書籍端末首位の米アマゾン・ドット・コムと競争が激しくなりそうだ。
配信する新聞はニューズ傘下のWSJなど数十紙。米紙ニューヨーク・タイムズや米紙ワシントン・ポストのほか、英紙フィナンシャル・タイムズなどが12月末から1月にかけて順次加わるとみられる。雑誌コンテンツは年明けから追加していく方針だ。
ニューズグループからは朝刊と同じ内容を早朝に配信する「WSJ」(利用料金月14.99ドル)だけでなく、その後に起きたニュースも加わる「WSJプラス」(月19.99ドル)の提供も受ける。WSJプラスは午後の配信もあり、日本でいう夕刊の電子版の機能も果たす。
市場ニュース中心の経済専門サイト「マーケットウォッチ」(月10.99ドル)と、初の電子書籍版となる大衆紙「ニューヨーク・ポスト」(月9.99ドル)はソニーの独占コンテンツになる。
ソニーがクリスマス商戦向けに投入した端末「リーダー・デイリー・エディション」を使えば、無料の無線通信で早朝や夕方といった定時にデータを自動的に取り込んでおき、好きな時に手軽に読める。アマゾンの電子書籍端末「キンドル」は同様の機能を備え、すでに新聞や雑誌が読めるようになっている。新聞・雑誌の配信で、ソニーがアマゾンを追撃する体制が整ったことになる。 |
5.電子書籍端末 ソニー、国内生産し輸出 海外委託との「仕分け」加速 |
| ソニーは電子書籍端末を国内で生産し、米国に輸出する。無線通信機能を搭載した新製品を岐阜県の自社工場で生産、月内に出荷を始める。同社はコスト低減のため液晶テレビなどで海外への生産委託を拡大しており、電子書籍もこれまでは中国生産だった。パソコンやリチウムイオン電池などでも先端機能を盛り込んだ競争力の強いものは使者生産が有利と判断。生産体制の「仕分け」を急ぐ。
月内に米国で発売する電子書籍端末「ソニー・リーダー・デイリー・エディション」を生産子会社ソニーイーエムシーエスの美濃加茂サイト(岐阜県美濃加茂市)で生産する。ソニーは手触りを重視して電子書籍端末の外装にアルミを使用。新製品は電波を妨げやすいアルミに無線機能を組み込むため、携帯電話などの生産実績がある美濃加茂サイトの技術を使う。
ソニーは2006年に米国で電子書籍端末の販売を開始、現在は米国とカナダに加え、英国やフランスなど欧州6カ国で事業展開している。米国でのシェアは現在、米アマゾン・ドット・コムが約6割、ソニーは3割程度のもよう。ソニーは市場の拡大が見込まれる同分野への取り組みを強化し、12年度に40%の世界シェアを確保する方針を示している。
アマゾンなどは電子書籍端末の生産に台湾などのEMS(電子機器の受託製造サービス)を活用、ソニーも従来はEMSに委託していた。ただ、無線機能を搭載した上位機種は自社生産して競合製品との違いを打ち出す。生産を通じて蓄積したノウハウを次世代製品の開発にも生かしたい考えだ。
ノートパソコンでも今秋発売した薄型軽量モデルについては長野県の拠点で生産する一方、普及機種では海外のEMSを活用する。リチウムイオン2次電池も福島県で生産し、グローバルに販売する。
デジタル家電ではソフトウェアの優劣が使い勝手を大きく左右して販売に影響を与えるとされるが、ソニーは「ソフトが一定水準に達したら、優れたハードを持っている企業が有利になる」(ハワード・ストリンガー会長)と判断。液晶テレビなど生産に関する付加価値が小さい製品は外部委託を増やす一方、違いを打ち出せる製品については自社生産する。
|
6.携帯電話を使い書籍を通販 GNT、大阪屋と組む |
携帯電話向け情報配信のGNT(東京・渋谷)は出版取次3位の大阪屋(大阪市)と組み、今月から携帯電話を通じた書籍の通信販売を始める。携帯を使う通販利用者の拡大を受け、自社の通販サイトを拡充する。携帯向けに特化した情報配信会社が、携帯の通販サイトで書籍を扱うのは初めてという。
大阪屋は商品提供を担当し、販路の拡大を見込む。GNTは自社の通販サイト「mobion(モビオン)」上で約100万店の書籍を扱う。GNTは2005年から携帯サイトを7サイト運営しており、09年度の携帯通販事業の売り上げは10億円程度となる見込み。
|
|